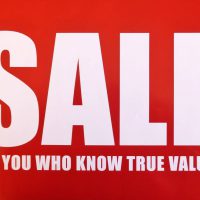やってはいけない決断方法
2016.06.09 | マーケティングブログ

決断する。社長はこれで迷う。
社長は基本的に一人だから自分で考えて決めるしかないことが多い。
決断は早ければいいってもんでもなくて何の考えも持たずにノリで決めるくらいなら決めない方がいいんじゃないかと思います。
いつの間にか決めることが目的になっちゃってる感じです。
かといってその考えの重要な部分を間違った方法から持ってきたら良い結果が出るはずもありません。
例えばこんなことがありました。
そのお店は小売店でショーケースを置いた店頭でパートのおばちゃんが販売しているようなスタイル。ショーケースの中には商品が並んでいてそれぞれの商品にプライスカードが置かれています。
その社長からの相談。価格を上げたいとのことでした。
訳を聞くとどうやら原材料の高騰らしい。原価が上がるからその分価格にオンするということです。
ただし原材料が上がる商品は限られてるからその商品だけを値上げすると。
その商品を使ったことある自分は以前から価値を感じていたので、もっと値段を上げていいんじゃないかって話は以前からしてました。ただ社長はそうすると高すぎて売れなくなるんじゃないかって懸念があって上げられませんでした。
そしてこのタイミングでの原材料高騰。
良いタイミングだから全ての商品価格を上げたほうがいいと提案するけど社長は渋ります。
じゃあ実際お客さんに価格のことを聞いてみたことはあるか?と聞くと聞いたことはないとのこと。でもお客さんからこんな話があったってことを聞きました。
それはお店のプライスカードの話。それぞれの商品の前に提示されてる価格表です。
そのプライスカードには「税込価格」のみが大きく記載されていました。
価格表示方法としては違法ではありません。
ただ、その価格を「税抜価格」だと思ってるお客さんが結構いるとのことでした。
税抜価格だと思ってたのに税込価格だったからレシート見てビックリみたいな感じ。
これは実際にお客さんに聞いた話だと言います。
価値で勝負する商品だからお客さんの価格感度なんてそんなもんです。
消費税分くらい上がってもそんなに気にならない。スーパーで買う夕食の材料と一緒にしてはいけません。
だから全部値上げしても大丈夫って話をします。
ちょうど原材料アップ分と消費税分が同じくらいだし、お客さんも税抜価格って思ってるんだったら今表示してる税込価格を税抜価格ってことにすればいいんじゃないかって話をします。
けどまだ渋ってます。価格を上げることにかなり抵抗がある。
そして「ちょっと考えてみます」ということでその話は終わりました。
その後2・3日してから社長から連絡がありました。
やっぱり価格を上げるのは原材料が上がった商品だけにするとの話。
「まだ伝わってないか」と思ってなぜそうしたかって理由を聞きました。
すると驚くべき回答が、、、
その理由は「パートさんが言ってたから」
ガーン!
ちょうどお店に来てる女性のパートさんがターゲット層の年齢に近いから聞いてみた、と。
するとウチの店はそもそも高いのにさらに値上げしたら買わなくなる、と。
そんなんで決めちゃうの?ってちょっと寒気を感じながら社長に伝える。
「社長、そんな大事なことをパートさんに聞いて判断しちゃダメですよ!そのパートさん社長のお店がつぶれても何の責任も取ってくれないでしょ?」
パートさんも良かれと思って言ったのかもしれないけど、そもそも値上げしましょうなんて言うパートさんなんているわけがない。別に自分が買うわけじゃないし、欲しいとも思ってないんだから安いほうがいいに決まってる。そんなの当たり前です。
出来レースになるような質問してその答えで判断ししゃダメです。
でも税抜価格だと思ってたって話は実際にお客さんが言ってた話。信じるならどっち?
その後、社長との話はもう一度考えるとのことで終わりました。
そしてまた連絡が来ました。
値上げ決定。
今度は奥さんと話して決めたとのことです。
そのお店は値上げに踏み切りました。その結果どうなったか?
売上5%アップ。客数変わらずで値上げ分売上が上がりました。
たった5%でしょ、って思うかもしれません。
でも注意してほしいのはこの売上アップ分はほとんどが「利益」だってことです。
だって原材料が高騰した商品はそんなにありませんから。
ほとんどの商品は単に値上げしただけです。
売上5%アップということは、利益率が20%の商品だったとしたら利益は25%アップになります。
年間で考えると3ヶ月分の利益が何もせずに増えたってことです。
それくらい値上げってのは利益にインパクトがあるものです。
その利益で自分の家族が暮らしてる。社員が暮らしてます。
そんな大事なことをパートのおばちゃんに聞いて決めようとするなんてのは完全な間違い。
「聞くならお客さんに聞け!」
ブログ執筆者